元禄時代の噂話や風聞などを集めた筆者不明の『世間咄風聞集』に、「松井与左衛門咄」がある。「高松藩松平家(12万石 香川県)下屋敷に保管する徳川家康から拝領の具足を含む武具を蔵役人が横領転売、証拠隠滅のため蔵ごと爆破しようとした」という話だ。
私はこの話を東京新聞連載の「東京ふるさと歴史散歩」に執筆するにあたり、高松藩の地元香川県立図書館に藩史料などの資料を問い合わせたが、「藩記録をはじめとする歴史資料に記載されたものは確認できなかった」という回答だった。
最後に「武具横領転売事件発覚時に藩主病気発症死亡」と「高松藩の親藩である水戸藩水戸光圀が将軍綱吉に疎まれていた史実」を記して、高松藩の記録にないこの「あわや御家の一大事」の事件を推測するうえでの参考に供したい。
【参考文献】
『元禄世間咄風聞集』長谷川強校注 岩波書店 1994(平成6)
『新修港区史』港区役所 昭和54年(1979)
『港区文化財のしおり 国都指定文化財編』港区教育委員会社会教育課文化財係 平成7年(1995)
『香川県立文書館紀要第19号』野中寛文「高松藩刑法と身分の利用」平成27年(2015) 『水戸市史中巻(一)』水戸市史編さん委員会 水戸市役所 昭和43年(1968)
『桃源遺事 水戸光圀正伝』稲垣国三郎註解 清水書房 昭和18年(1943)
『江戸の刑罰』石井良助 中公新書 1964(昭和39)
白金「地名の由来と変遷」高松藩屋敷から軍用地・宮内省御料地へ
港区内を走る首都高速目黒線沿いに広大な森が広がっている。都内で武蔵の面影をしのぶことのできる数少ない場所で、国立科学館付属自然教育園と東京都庭園美術館(白金台5丁目)がある。

▲高松藩下屋敷のあった東京都庭園美術館の旧朝香宮邸 写真松本こーせい
この地は室町時代に南朝の下級役人がこの地を治め、自然教育園にみられる地形を利用して、城砦式の館を築いた跡だ。この役人が大量の銀を所有していたことから「銀長者→白金長者」とあだ名され、これが「白金」の地名の由来となったとされている。
なお『港区文化財のしおり 国都指定文化財編』によると、この地は「南北朝期の白金長者の屋敷地として史跡にも指定されているが、根拠原典の『文政町方書上』には、その屋敷地は教育園の敷地内ではなく、現在の品川区上大崎にあったことが明記されている」という。
その後、江戸時代に高松藩(12万石 香川県)の下屋敷となり、明治以降は軍火薬庫、宮内省御料地などへ推移。一般人の立ち入りが禁止されたため、昔ながらの自然が残されたのだという。
高松藩の記録にない「下屋敷武具横領転売・証拠隠滅爆破未遂」
高松藩下屋敷の武具横領転売・証拠隠滅爆破未遂事件を記した『世間風聞集』とは
岩波文庫『世間風聞集』は同書について次のように解説している。
元禄七(一六九四)―元禄一六(一七〇三)年の間の江戸の噂話を書き留めた書.浅野内匠頭の刃傷沙汰をはじめ、生類憐み令にふれた科で処刑された事件、旗本の乱心,姦通などの醜行,落語「野晒」の原話などを収める.浮世草子等の源泉となった雑記類の多くが散逸した中では希有の生残りである. 元禄時代の裏面を語る興味深い資料.付・索引. 岩波文庫「解説」 はこちら https://www.iwanami.co.jp/book/b245934.html
高松藩下屋敷の「武具横領転売 証拠隠滅爆破未遂事件」
高松藩の下屋敷「目黒屋敷」(港区白金台5)は旧朝香宮邸の庭園美術館から自然教育園の南側にあった。蔵屋敷を兼ねたこの下屋敷で、元禄15年(1702 5代綱吉)に「土蔵管理役らによる武具横領転売事件」が発覚している。水戸藩主徳川光圀(水戸黄門)の子、松平頼常が藩主時代のことだ。
この武具横領転売事件は、土蔵管理役が病気で交代したことで発覚した。藩は武具の管理をこの役人に任せていたため、5、6年前から犯行を重ね、門番も犯行に加担していた。藩の国元である讃岐の者が下屋敷の近くに家を借り、その借家に武具を持込んで質に入れていたのだ。
上屋敷(千代田区飯田橋)の者が武具の虫干しに来訪すると、管理役の男はそのたびに「もう虫干しは済ませた」「今日は取り込み中なので、明日自分が虫干しする」と理由をつけて土蔵内を見せず、ごちそうで接待してごまかし続けたという。

2008年(平成20)
やがて犯人の男は病気で管理役をつづけられなくなったため、武具横領転売の発覚を恐れ土蔵を爆破して証拠を隠滅しようとしたが捕まった。土蔵の中は空で、5、6千両相当の武具が消えていた。
藩主水戸頼常の父の光圀は、15万両出すから武具を買い戻すよう指示したが、買い戻せたのは徳川家康より拝領の700両相当の具足だけだったという。
香川県立図書館と文書館「武具横領資料は見つからず」
東京新聞「東京ふるさと歴史散歩」に「武具横領事件」を執筆するにあたり、高松藩の史料を活用するため香川県立図書館にレファレンスをした。しかし意外なことに、この重大事件についての「資料は見つからず、香川県立文書館にも問い合わせたがわからなかった」とのことだった。
「家康から拝領の具足を含む武具を家臣が横領」というこの大事件は、江戸の単なる噂話か? それとも御家の一大事だとして藩記録に記すのをはばかったのか?この事件に興味を持ち、調べてみようとする人もいるかもしれないので、ご参考までに県立図書館が調査した資料が列挙された「回答」を添付する。
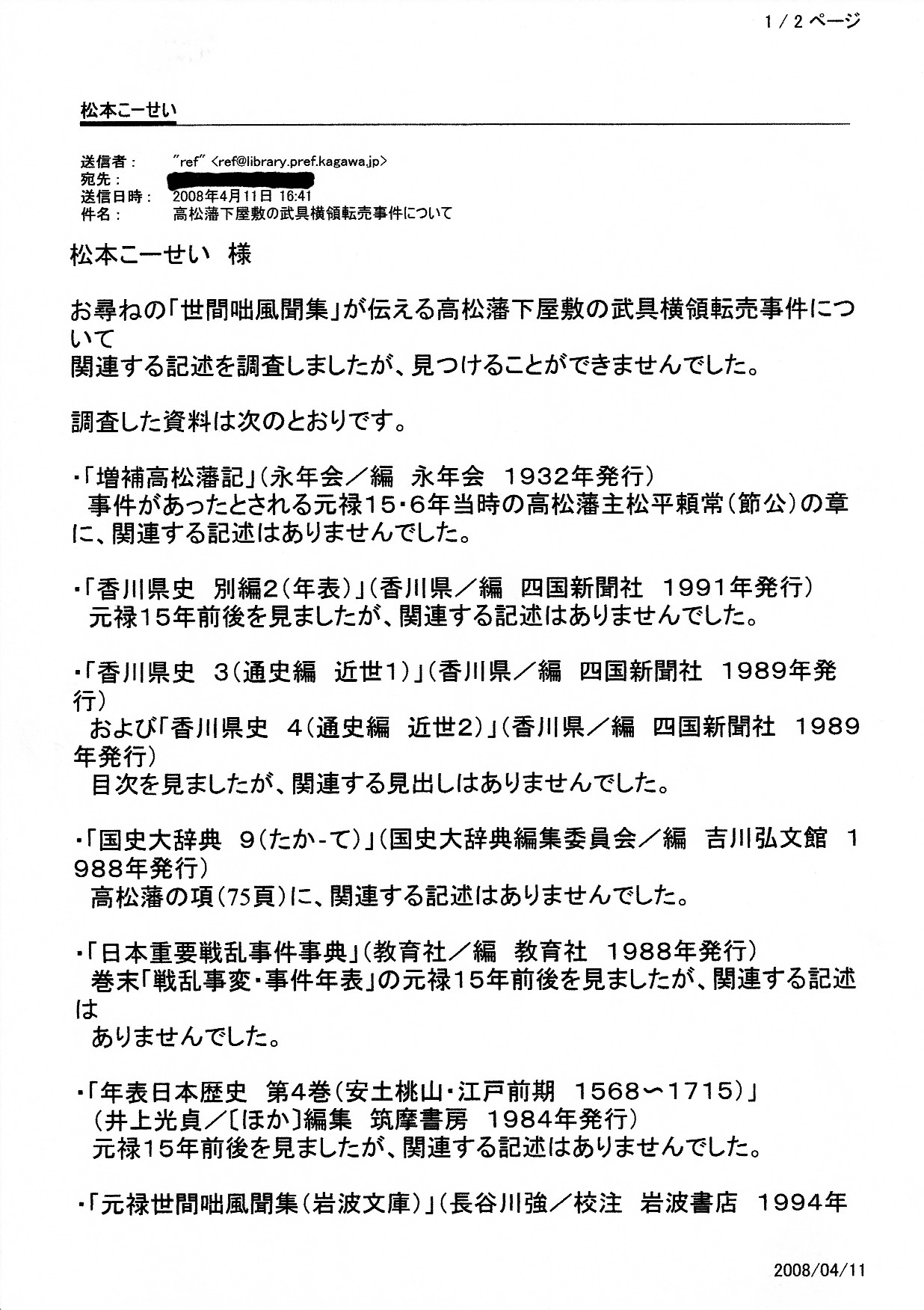
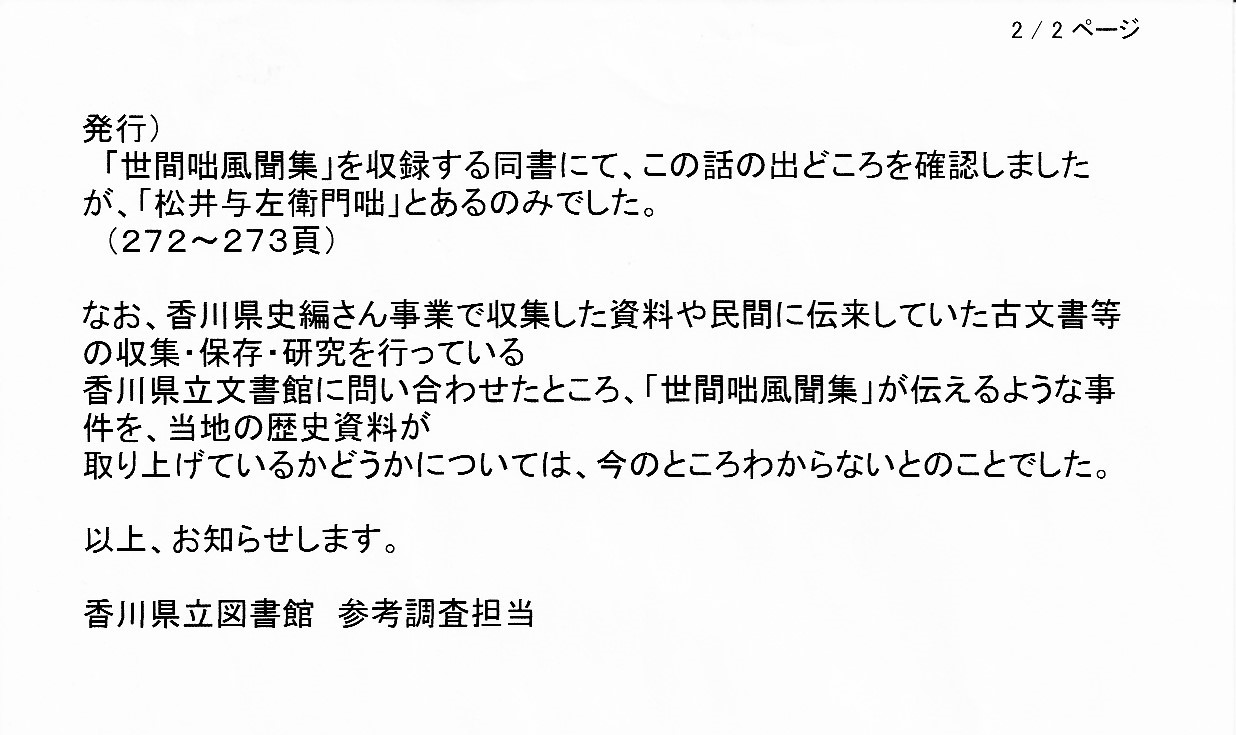
事件が事実なら処分は?大名屋敷の大名と幕府の処罰権
この事件に関する記述は『元禄世間風聞集』だけなので、以下の事項を紹介して藩記録にないこの事件を推測する材料に供したい。
・高松藩の刑罰
・高松藩主の善政と事件発覚年の体調不良と死去
・将軍綱吉に疎まれていた水戸藩主徳川光圀
『世間風聞集』には主犯の土蔵役人とその家族、それに共犯の門番等の吟味の記述はあるが、彼らの処罰については記されていない。そこで参考までに、事件から45年後の延享4年(1747 9代家重)に出されたものだが、「高松藩の御仕置之仕方」による重罪の処罰の一部を紹介する。
幕府の刑罰
石井良助『江戸の刑罰』(中公新書)によると、各刑罰の意味は次のようなものだ。
磔
古主殺、親殺、師匠殺、主人傷つけ、関所をよけて山越えした者などに科す。
斬罪 斬首
死罪と同じように「斬首」の刑。その者の田畑、家屋敷、家財は闕所(財産没収)になる。士分(武士身分)以上の場合には「斬罪」と呼ぶ。斬罪は武士や僧侶・婦女・老若・廃疾の者に、本刑の代わりに科す寛大な刑「閏刑」。
梟首
獄門の古称で晒首のこと。罪の重い者にはさらに引廻が付加され、引廻のうえ牢内の切場で斬首したのち、晒首にする。
高松藩の刑罰「高松藩の御仕置之仕方」
『香川県立文書館紀要第19号』野中寛文「高松藩刑法と身分の利用」
附火人 磔
人殺 磔あるいは斬罪梟首または於籠屋敷に討捨
御城御林江入り候盗賊人 磔または斬罪梟首
銀子似セカネ師 斬罪梟首
御家中江入り候盗賊人 斬罪梟首 または御国追放
押入盗人 斬罪梟首 または磔
討ち捨て 牢屋内死刑場で打首になった死骸は葬ることができない
取り捨てるべきものなので江戸では本所回向院の千住の寮へ埋めた
御国追放 追放刑は幕府のみでなく、諸藩でも領分構(領分払い)と称し、
旗本領でも知行払と称して行っていた。
下屋敷武具横領事件発覚の影響か?高松藩主の体調不良と死去
第2代藩主松平頼常は藩の倹約令を率先実行して藩財政を改善、凶作時には困窮者の救済をはかり、藩の綱紀引き締めをはかるなど善政を実行。武具横領事件発覚の元禄15年(1702 5代綱吉)に体調を崩し、翌年死去した。
元禄8年(1695 5代綱吉)
倹約令を出して藩主自ら倹約実行。20万両程度の小判を貯えた。風水害や日照り、干ばつにより稲の凶作がつづくと、松平家別邸「栗林荘」の庭普請(現・栗林公園)に困窮者を雇い、賃金米を与えて餓死を防いだという。
元禄9年(1696)
法令や条目を制定して藩の綱紀の引き締めをはかる。
元禄16年(1703)
高松藩下屋敷武具横領事件が発覚したこの年の秋、頼常病気になる。
宝永元年(1704 6代家宣)
藩主を養嗣子の頼豊(初代藩主頼重の孫)に譲り、江戸屋敷で死去。
将軍綱吉に疎まれていた水戸藩主徳川光圀
「高松藩下屋敷武具横領事件」が事実だとしたら、それを藩記録に記さなかった理由は?
徳川御三家水戸藩の支藩である高松藩が、「神君家康公から拝領の武具等を家臣が横領転売」という大失態が公になるのを避け、親藩である水戸藩の故徳川光圀(水戸黄門)が時の将軍綱吉に疎まれていたので、御家の一大事になるのをおそれたからだろうか。
綱吉と光圀との関係性悪化を示す「光圀の書状」
『水戸市史中巻(一)』水戸市史編さん委員会 水戸市役所 昭和43年(1968)
将軍綱吉がわが子徳松を世子に立てようとしたとき、光圀は綱吉の兄、故綱重の子綱豊を立てることを勧め、また綱吉が娘の婿、紀伊家の綱教を江戸城西丸に住まわせようとしたときも、西丸は将軍世子の住む所だから名分が合わないといって、賛成しなかった。幕府の生類憐みの令にも反対であった。
これらの事から、綱吉に疎まれるようになり「御一生の内、くひちがひたる事のみにて御過しなされ候」と「桃源遺事」※に記されている。
また光圀が生類憐みの令に従わず、わざと狩りに出て殺生したことや、鍋島元武をはじめ親密の大名・旗本の有志と千寿会という風雅の会を作って時々集まっていたこと(風雅に託して時勢の事なども談合したらしい)などが、近年鍋島元武宛光圀書状(茨城県立図書館所蔵)で明らかとなった。
※筆者(私)注 「桃源遺事」は水戸光圀の伝記
『桃源遺事 水戸光圀正伝』稲垣国三郎註解 清水書房 昭和18年(1943)
国立国会図書館デジタルコレクション インターネット公開 <https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1030760>


